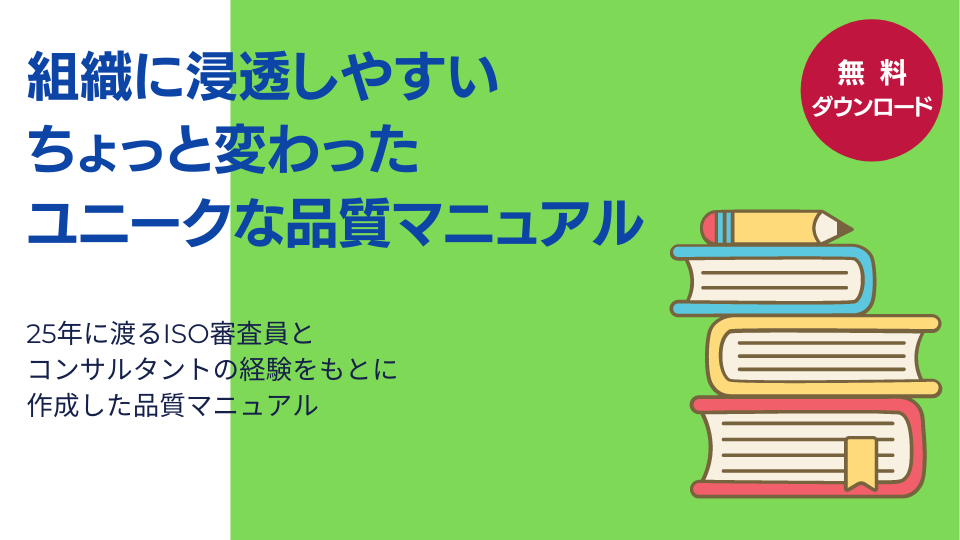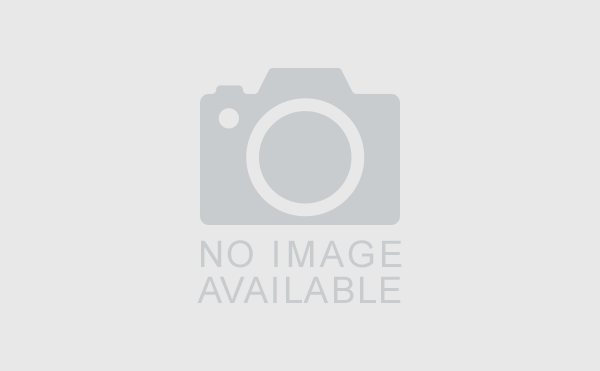ISO内部監査は、うまくいっているか?(無駄・マンネリを防ぐ)

ISO審査員している立場上、内部監査の記録を通じて、内部監査の状況を伺い知る機会が多くあります。
残念ながら、「上手に内部監査をしているなあ」と思える組織には、めったにお目にかかれません。
淡々と、予め用意されたチェック項目を毎回毎回、確認し、「はい、やってますね」で終わっていれば、全くもったいない話です。
ISO内部監査に取組む組織によくある風景
多くの組織で、次のように感じていることが多いようです。
- 本審査を意識しての審査のリハーサル的審査になっている。
- 適合しているかをみており、固定化、儀式化している。
- 要求事項項目の最初からみていき、いつも規格の前半の部分で時間が切れる。
- 目的が薄れている。
- 核心に迫れない。
- 机上の監査が中心になっている。
- 監査力量にバラツキがあり、監査結果に差異が生じる。
- 事前準備が不十分。
- 監査員に割り当てられると、面倒くさい。
- 指摘は、なるべく受けたくない。
大切なことは「問題意識」。
同一組織内であっても、意外に、他部門の仕事のやりかたは、承知していないもの。
内部監査は、他部門の方の仕事のやり方を、知る絶好の機会です。
そんな中、問題意識さえもっていれば、気づき事項を多く検出できるはずです。
さて、それでは、監査を充実させるために、どうすれば良いのでしょう??
ここ3年の間に、大手の会社から、内部監査を既に実施ている方を対象とするブラッシュアップ内部監査研修を承る機会(4~5回)がありました。
基本的に次のように進め、今後の監査の取り組み方や内部監査プログラムの改善に役立てていただいています。
ISO内部監査の無駄・マンネリを防ぐポイント(内部監査員研修より)
内部監査員研修にて、
”現状の内部監査に対する印象は?”をまず最初に問うことにしています。
数名で、意見交換をしてもらい、公開してもらっています。
以下が、よく聞かれる内容です。(上記と同じ)
- 本審査を意識しての審査のリハーサル的審査になっている。
- 適合しているかをみており、固定化、儀式化している。
- 要求事項項目の最初からみていき、いつも規格の前半の部分で時間が切れる。
- 目的が薄れている。
- 核心に迫れない。
- 机上の監査が中心になっている。
- 監査力量にバラツキがあり、監査結果に差異が生じる。
- 事前準備が不十分。
- 監査員に割り当てられると、面倒くさい。
- 指摘は、なるべく受けたくない。
良い監査とはどのような監査なのか??(現状とのギャップを自覚する)
では、良い監査とは、どのような監査でしょうか?
これについても、同様に、意見交換と公開をしてもらっています。
すると、”現状”と”良い監査”との乖離が認識され、これを埋めていくことが、今回の監査研修のねらいとなります。
監査の要求事項、基本知識 から
監査ステップ (計画~準備、実施、報告、フォロー) の一連を
同社の仕組みに準じて、
実際の監査に可能な限り、近い環境にて行い改善内容を考察しながら、進めます。
ふさわしくない監査の代表格はこの2点。
中でも、よく見かけるふさわしくない監査の代表格として
- 規格順番とおりにする
- 予め想定した質問をひとつづつ順番にこなしていく
といった点があります。
これらに対しても、チェックリストを考察しながら、
目的に適った、核心に迫れ得る審査方法を追及します。
-
- 監査の指示をどのように行うのか?
- 適合審査に加え、有効性をどうみるのか?
- どんな順番で審査を行うのか?
- どこで、だれに、質問をすと良いのか?
- サンプリングをどのように行うのか?
- 現場審査では、何をサンプリングするのか?
などなど、考え出せば、マンネリや形骸化などとは成ろうはずがありません。
内部監査の在り方に疑問を感じているル中小企業ISO推進者の方には、ぜひ1歩踏み込んでいただきたい。
公開研修でのモデル企業を想定してのシミュレーションとは異なって、企業内でのリアルなやり方と内容で行う内部監査研修は、効果的です。
これまで、凝り固まって実施していた内部監査のありかたを考察する良き機会になるものと思います。
日頃、内部監査の在り方に疑問を感じているル中小企業ISO推進者の方にも、1歩踏み込んでいただきたいものです。